朝礼・empathyと日本文化
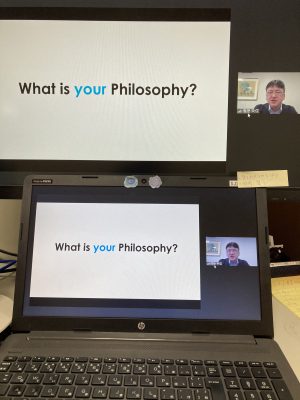
先週は中等部、今朝は高等部の朝礼をオンラインでやりました。
高等部校長の権藤から、企業や大学のミッションの話、個人の哲学の話がありました。

「握った拳では握手できない」非暴力のことですね。

以前、緒方さんにお目にかかる機会があり、「 中高生が将来のため身につけておくべき力は何ですか?」 と伺ったところ、一言、「エンパシー」 とおっしゃったことが思い出されました。
empathyは、日本語の同情と近いニュアンスのsympathyと違い、自分と違う考え方や価値観を持っている他者の立場に立って、状況や感情を理解することだそうです。
そして、他者の立場に立つためには、自分を理解しておくことも必要です。
先日、日本文化の研究をしているJef Berglundさんの講演を聴き、このエンパシーの話と共通することがあるなと感じたので、(私の理解ですが)印象に残ったことをシェアします。
他者を理解する際の順番として、以下があり、他者(他文化)に対する違和感は大切で、学びのきっかけとなる。
1、 Observe(意識を働かせて見る)
2、 Borrow( 他者の目を借りて見る)
3、 Integrate(統合する事で受容の「器」が広くなる)
(本校で「もめ事は大事」と言っているのも、それが、自分と違う考え方とぶつかり、伝え合い、統合していく過程だからだなと再認識しました。)
また、欧米が「発信者責任文化」であるのに対し、日本は「受信者責任文化」で、日本人は受信力が強く、相手の気持ちを読み取ってコミ ュニケーションするともおっしゃっていました。
もちろん個人差はありますが、こうした文化を私たちが背景に持つとしたら、これを認識して活かしていきたいです。
本校で取り組んでいるデザイン思考にも、このエンパシーを知的に働かせ、一つのスキルとして高めていくとトレーニングが含まれています。
