家庭科の特別授業
家庭科の特別授業をご紹介します。 担当の山下より報告です。 *毎年、家庭科の授業で行っている、金融教育の報告です。 4年家庭基礎にて、お金の教養講座を実施いたしました。ファイナンシャルアカデミーの講師の方々に来ていただき、 全クラス2時間ずつ講義をしていただきました。この講座は今年で11年目となります。普段は友達や家族とも中々話さないお金の話。例えばブランド品やスマホは新品を買う?中古品を買う?といった身近な話から、リセールバリューのあるものを考えたり、住宅ローンの金利について学んだり、幅広いお金の知識を教えていただきました。ちょうど日銀の政策金利の引き上げが発表されたタイミングで、バブルの頃と最近の金利の違いなどを示しながら、今後どう推移していくかまで含めたお話をしてくださり、経済との繋がりを直に感じたという感想もありました。生徒たちの感じ方は人それぞれで、地方のマンションであれば、20代でも買える!とワクワクする生徒もいれば、都心部のマンション価格を知って、必要な収入を逆算していくと結構厳しいかも...となる生徒も。住みたい家(の価格)から逆算して、職業→進路を決めていくのも面白そうという声もありました。講師の方が仰っていたように、同じ話を聞いているはずなのに、大人になるのが怖いという生徒もいれば、大人になるのが楽しみと全く違う感想があるのも面白く、それぞれの考え方が表れる時間になっていました。今回は講座後に、授業で「1万円以内で価値を感じるもの」をグループごとに考え、プレゼンする機会を設けました。ツアーコンダクターのように、登山や日帰り旅行を提案するグループもあれば、小動物を購入し一時的ではなく一緒に過ごす時間にも価値があると考えるグループや、親孝行など家族でのご飯に使う、あえてゲームセンターなどで浪費する、という声もありました。「シンクライフ、シンクマネー」講座の中のこの言葉が指すように、生活や人生を考える上でお金の話は切り離せないもの。そんな視点を持ち、自分の人生を送れる生徒が増えたら嬉しく思っています。ファイナンシャルアカデミーの小野原様、 今年度もありがとうございました。 *4年生の「家庭基礎」の授業にて、一般社団法人ソウレッジ様による特別授業 を実施いたしました。 ソウレッジ様は「 性教育と避妊の支援で長期にわたる悲しみの減少をめざす」 を理念に、ユースクリニック普及のための海外研修、 緊急避妊薬の無償提供、 性教育などを含めた政策提言などを行なっています。 代表の鶴田様と副代表の鈴木様にお越しいただき、今回は「 性のトラブルを予習して実際に起きた時に適切な対処をできるよう になる」ことを目的に、 ボードゲームを用いたワークショップを実施していただきました。 最初の講義では、事業内容の紹介や、 海外では5歳から性教育が始まることや、 ユネスコの国際セクシュアリティ教育ガイダンスの内容のうち、 日本の教育で教えているのはごく一部であることなどを教えていた だき、その後グループに分かれゲームがスタート。すごろく形式で各マスにケースの内容が書いてあり、 クイズに答え→グループで対話し→解説を読む、 という流れで進んでいきました。 わいわいと楽しそうに、グループで対話や経験談を共有し、 盛り上がっている姿が印象的でした。 ボードゲーム後の質疑応答の時間では、月経や中絶、 痴漢など多岐にわたる質問が出ました。一つ一つの質問に丁寧に答えていただき、 特に低用量ピルや子宮内システム、 日本での未承認のパッチなどの話に生徒たちは驚いていました。 有志団体のCLAIR.に所属している生徒からは「 日本の性教育の遅れを感じる中、 生理以外についても課題がたくさんあると体感できた」 という声もありました。その他にも「学校で学ぶことができないと思っていたことだった」 「知らないを知ることができ、 自分の身を自分で守ることができそうだと思った」「 友達とこのような話を今までする機会がなかったが、 話し合える良い機会だった」といった声もあり、 学びの多い充実した時間となったようです。 ソウレッジの皆様、貴重な機会をありがとうございました! *こちらも4年生の「家庭基礎」の授業の報告です。スリール株式会社様による特別授業を実施いたしました。 スリール様では企業向けの女性活躍やDE&I推進に加え、大学生向けのキャリア教育(ワーク&ライフ・インターン)を行っています。私も学生時代にワーク&ライフ・インターンに参加しており、共働きのリアルを体感し、将来の輪郭が少しはっきりとしたのを覚えています。 今回は子ども家庭庁のプログラムの一環として、将来に向けて自分の「なりたい姿ワーク」と、実際に子育て中の方に子ども連れで来ていただき「パパママ先生インタビュー」を実施していただきました。 「なりたい姿ワーク」では、授業の中で考えたLife visionのワークシートをもとに、それを実現するための壁があるか、それはどんなものか、なども深掘りして考えました。スリールの講師の方は2名とも副業をされている方で、仕事やプライベートも含め、様々な選択肢があることをお話していただきました。 「パパママ先生インタビュー」では、2〜3グループに分かれ、仕事や子育てのお話を伺いました。普段はなかなか赤ちゃんと接することのない生徒たちですが、赤ちゃんが登場すると大歓声が!授業が終わった後も抱っこさせてもらったり、様子を微笑ましそうに眺めていたりと、いつもとは違った生徒の表情が見られたのも印象的でした。 事後アンケートでは、「仕事を楽しいと思えるような職業に就こうと思ったし、自分が楽しいと思えるような企業で働いてみたいと思いました。実際に赤ちゃん見て私も育てたいと思いました。」といった感想や、「あまり子育て世代の大人と話す機会がなかったのでとても新鮮で楽しかったです!」「赤ちゃんがとても可愛く、パパママ先生の人生が楽しそうでした。」といった声がありました。 本校の生徒たちは「働く」ことについて強い関心があると感じますが、一方でキャリアを積むこととライフイベントが重なることもあり、両立できるか不安に思っている生徒もいます。実際にパパママ先生の話を聞き、子どもと接してみることで、将来のイメージが少しでも描けたらと思っております。 スリールの皆様、貴重な機会をありがとうございました! この特別授業について、先方からプレスリリースが出ましたので紹介します。 スリール株式会社、中学・高校の家庭科授業で ライフキャリアデザインを実施~授業を通じて中高生の結婚や子育てに対する意識が大きく変化~
2年生日本文化の授業
今年も、2年生では日本文化の授業が行われました。 茶道は、臨時にしつらえた作法室で工夫して行ってきましたが、新校舎には素敵な作法室が完成しているので、楽しみです。 <1回目> 心は水中の月の如し <2回目> 大道は長安に透る(通る) <3回目> 独り慎む <4回目> 無事是貴人 こちらは、いけばなの授業の様子です。 <1回目> 1回目は、レクチャーと、デモンストレーションです。 <2回目> <3回目> 能楽も毎年鑑賞しています。 学年主任の住谷より以下報告です。 期末試験の終わった翌日、2学年では総合学習テーマ「 日本を知る」の一環で、観世九皐会の皆様に来校していただき、 体育館を舞台に能楽を鑑賞しました。 まずは狂言「柿山伏」から。 喉が渇くあまり勝手によその家の柿の実を食べてしまった山伏( シテ)と、それを見つけた主人(アド) とのコミカルなやり取りに、 生徒からもクスクスと笑いが起きていました。 続いて能で使用される楽器の紹介へ。奏者の登場の際、 女性奏者がいらっしゃるのに驚く生徒たち。 男性の芸能という印象が強かったようです。小鼓は湿気が必要、 大鼓は乾燥が必要という違いも意外でした。 休憩をはさんでいよいよ能の番に。今回は半能「敦盛」 を鑑賞しました。源平合戦の一つ、 一の谷の合戦における平敦盛と熊谷直実の決戦、 そして亡き我が子と同じ16歳の敦盛を討ち取ったものの、 世の無常に苦しむ直実が出家する様をたった2人の演者と奏者で演 じる様に見入っていました。 ちょうど今年から古典文法を習い始めた2年生、 難しい言葉遣いの合間に聞いたことのある言葉を耳にしたようで、 学習の成果を発揮した人もいたようです。 最後にワークショップ。 各クラスから出てきてくれた代表生徒を前にしつつ、 みんなで狂言の構えの姿勢をとり、「柿山伏」 で出てきた動物の鳴きまねに挑戦。 最初は恥ずかしがっていた人もみんなでやれば怖くない?、 大盛り上がりでした。 一緒に鑑賞していた本校に在学中の留学生も、 文化の壁のないパフォーマンスに楽しそうでした。 今回能を初めて鑑賞した生徒が非常に多かった中、感想には、 古典芸能と言われている歴史的な能だけれど、 今の私たちにも理解ができることがすごい、 表現の仕方が独特で面白かった、 このまま未来にも残していきたい、 などたくさんの刺激を受けた様子が見られました。 日本の伝統に触れ、それをどう受け継いでいくか。 3学期に実施する生け花の授業や3月の京都宿泊研修に向けて、 同様に考えていくテーマでもあります。 少しでも生徒たちの意識にとどめることができればと思います。 観世九皐会の皆様、本当にありがとうございました。
地域との交流・お知らせ
本校は社会とつながる活動を大切にし、それぞれの学年や有志グループが活動しています。品川の地で100年の学校でもあるので、地域との交流も大切にしています。 担当の河合から報告です。 防災に関する品川区の森澤区長とのタウンミーティングに防災有志 の生徒数名が参加して参りました。 「品川区での共助の課題について考える」というテーマで, 行政の担当者,地域住民,立正大学, 近隣他校の方々とディスカッションをし, 最後には生徒たちからお願いをして, 森澤区長と集合写真を撮っていただきました。 引き続き,行政とのつながりも大切にしていきます。 12月3日には、品川区主催の産学官連携フォーラムに学生団体「Like me」と「charme」が招待され、各団体の取り組みについて発表の機会をいただきました。 担当の塩崎より報告がありましたので、PDFを添付します。 産学官連携フォーラム「「ともに創る 自分らしくミライを実現する都市」~世代をこえたリーダーたちと考える未来都市しながわ~」参加報告.pdf (3.92MB) 北品川ゆうゆうプラザでネイルサロンレクを行った班が、第2回のイベントを実施しましたので、 ご報告させていただきます。(1回目のイベントの様子はこちら) 今回は北品川ゆうゆうプラザの利用者のみなさまを品女にお呼びし て、班員だけでなく品女生からも希望者を集め、 合計23名でガトーショコラ作りを行いました。 そのときの様子をゆうゆうプラザのブログにてご紹介いただいてお ります。中高生とLet's cooking ケーキをつくりながらクリスマスパーティー♪♪ 参加された皆様からは、ケーキ作りというより、 普段かかわることのない世代同士での交流がなにより楽しかった、 とお声をいただきました。 CBLとしての活動は今回で終了となりますが、 このご縁を繋いでいけるよう、形を変えて定期的にイベントを開催していきたいと考えております 。 *今年度、登壇した会議の様子がHPで公開されましたので紹介します。 あすか会議2024 「アントレプレナーを生み出す教育~これからの時代の人材育成の手法を考える~」漆紫穂子×水野雄介×山口文洋×鈴木寛 【知見録記事URL】https://globis.jp/article/tuno 2ju4_k/ 【Youtube】https://youtu.be/aTj4fZ7hpVo *日経XWomanにて、シフターフッドについて取材された記事が掲載されました。有料記事ですが紹介します。 ゆで卵1200円に驚愕… 品川女子理事長が日本に必要と痛感したもの
経産省ワークショップ(20250324)
神山まるごと高専さん、東京都立産業技術高専さん、開成高校さんの生徒の皆さんと共に、経産省に行ってきました。 政策について現場のリアルな声も聞けましたし、各校それぞれの持ち味が出た議論になっていたように感じられ、3時間半、見ていて全く飽きませんでした。 このような機会をいただけたことに、感謝申し上げます。
図書室引越日記 #10 本はすべて箱の中である
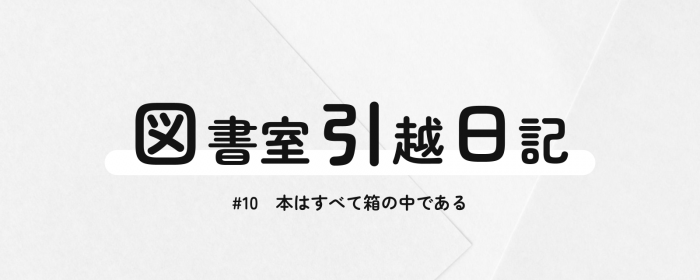
本はすべて箱の中である。 少し前の話ですが、業者の方に手伝っていただき、図書室の本はすべて箱に。 次の投稿からA棟での様子をお伝えします。 図書室 岩崎 図書室引越日記 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9
修業式のあと(20250322)
演出家の木村龍之介先生を講師にお迎えして続けてきたシェイクスピア特別講座。今日はその成果発表会でした。 題して、カジュアルな『ロミオとジュリエット』in品女 びっくりしました。 あんまり驚いて言葉が見つからないという経験を久々にしました。 講座の回数の関係で、身体の動作を少なくし、台本を見つつのセリフ劇でしたが、自分たちなりに戯曲の言葉を消化し、自分の表現として構築していました。 言葉に力がありました。 直前に一人一人に指導の時間を作ってくださった木村先生のマジックでもあると思いました。 いいものを見せてもらいました。ありがとうございます。 (バルコニーのシーン)
クラウドファンディング(20250321)
2年生の生徒から、学校外で打ち込んでいる活動について、報告と応援の依頼がありました。 直接頼まれたので、私も少しだけですが支援します。 皆様も、よろしければ、ぜひ。
答案返却日(20250312)
生徒の皆さんは、期末試験の結果が返ってくる日。 全然関係ないのですが、校長室が広くなりました。 窓もつきました! (これからもうちょっと備品が入ります。)
卒業式祝辞

今日は本校77期生の卒業式でした。天候にも恵まれとてもよい式が挙行できました。15年間の建築プロジェクトを経て、ようやく竣工した講堂で行う初めての式典となりました。工事期間は不便な思いをさせることが多かったので、この創立100年というタイミングに彼女たちをピカピカの校舎から送り出せたこと、本当にうれしく思いました。祝辞でお話しした内容をこの場を借りて皆様とシェアしたいと思います。 振り返ると、コロナ禍により多くの制約があった一方で、本校として初めてのチャレンジを数多く行った学年でもありました。 1年生ではデザイン思考、3年生では起業体験プログラム、4年生ではチャレンジ・ベースド・ラーニング(CBL)に取り組みました。また、起業体験プログラムはクラスを超えて実施され、5年生では個人探究に挑戦。そして、引っ越し前の講堂で行われた卒業式と、ほぼ毎年新たな試みが行われてきました。こうした取り組みが現在では定着しているのは、本校の「品女DNA」ともいうべき、「文句を言う前にまず行動」という起業マインドを、皆さんが実践してくれたからこそだと思います。 さて、この「品女DNA」につながる昔話をお話ししましょう。今から100年以上前、日本には女性が学べる大学が一つしかありませんでした。幸運にもその大学に入学を許された女性がいました。彼女は、その恵まれた環境に感謝し、いつか社会に恩返しをしようと一生懸命勉強していました。しかしある日、父親から退学を命じられました。理由は、結婚のため。彼女は一週間泣き続けた末、父の命に従いました。当時、女性には選挙権がなく、国のルールのすべては男性によって決められていました。それだけでなく、自身の進路や結婚相手も親が決めるのが当たり前でした。しかし彼女は、そのとき一つの決意をしました。 「次の世代の女性たちには、自分の人生を自分で決める自由を与えたい。そのためにできることは何でもしよう。」これは、私がこの学校の創立者である漆雅子から聞いた話です。 彼女は、自由を得るためには自立する力、すなわち経済的な力が必要だと考えました。そこで、女性たちに手に職をつけさせるため、裁縫を教える場を設けました。これが、この学校の前身である「荏原女子技芸伝習所」の始まりです。「女性が自らの人生を選択できるように」「女性が国家の意思決定に参加できるように」—— こうした志を持ち、100年の歴史を歩んできました。今日、この学び舎を巣立つ皆さん。自分の進路を決める際、少なくとも自分の意見を反映させることができたのではないでしょうか。 では、日本という国はどうでしょう?私はこの一年、次の100年も品女の教育が続くよう、多くの方に協力をお願いしてきました。本校からは多くの卒業生が社会に羽ばたき、起業マインドを持ち、ゼロからイチの価値を生み出せる人が育っています。そのことを、私は確信しています。 これは、身びいきの主観でなく、卒業生の調査研究からも明らかになっています。 しかし、ジェンダーギャップを解消するために女子教育への支援を呼びかけると、反応は大きく二つに分かれました。一つは、「自分には力がないけれど、できることは何でも応援する」というもの。 もう一つは、「それは素晴らしいことですね。品女さん、頑張ってください」というものです。個人差はありますが、前者は主に女性や若手、後者は日本の政治や経済の意思決定層の男性に多く見られました。衆議院の女性議員比率は、2024年で15.7%、東京証券取引所のプライム市場に上場する企業1,836社のうち、2023年1月時点では女性社長はわずか15人で、全体の約0.8%、つまり社長が100人いたら女性は一人いない割合です。 高等教育を受けた女性が報酬を得られない国としてもOECD断然の最下位です。人口減少が進むこの社会において、国の半分を占める人的リソースを十分に活用できていない現状は、まさに危機的状況といえます。 私自身、これまで女性への差別をほとんど感じることのない人生を歩んできました。しかし皮肉にも、この活動を通じて、日本がなぜジェンダーギャップ指数において依然として世界118位なのかを痛感することになりました。100年たっても変わらないこの状況を、次世代に引き継いでは申し訳ない、これは私たち世代の責任だと思うようになりました。そんなとき、たまたま出会ったのが、映画『ハリー・ポッター』のハーマイオニー役として知られるエマ・ワトソンが国連で行ったスピーチ「HeForShe」でした。そのスピーチから私が得た学びは、男女の対立構造にしてはいけないということでした。男性対女性ではなく、「みんなのために」。 例えば、第二次世界大戦の開戦決議をしたアメリカの下院議会では、戦争賛成票が388票、反対票が1票でした。賛成票を投じたのはすべて男性議員であり、唯一反対票を投じたのは米国初の女性議員、ジャネット・ランキンでした。また、本校の校歌の作詞者である与謝野晶子は、日露戦争のさなかに「君死にたまふことなかれ」と歌いました。意思決定の場には多様性が必要なのです。 女性のためだけでなく、すべての人のために。未来に向けてこの国を支え、そのプレゼンスを高め、世界の平和に貢献するために——。この共通の目標に気付いてから、男性の意思決定層にも少しずつ応援してくれる人が現れるようになりました。 さて、皆さんは今日、この学校を巣立ちます。皆さんが過ごしたこの環境は、思った以上に特別なものであったことに、いずれ気付くでしょう。今や、公立高校の99%が共学化する中、私立女子校という、男女の役割バイアスから自由な環境で過ごした6年間で得たものは、貴重な財産となるはずです。 校歌の「われら平和の使い」を胸に、さまざまな対立を乗り越え、共通の目標を見つけ、社会に価値を生み出す人であってください。「自分がそこまでしなくても」「まだ力不足だから」—— そんなふうにくじけそうになったとき、エマ・ワトソンの言葉を借りて、自分に問いかけてみてください。 If not me, who? If not now, when? そして、疲れたときは、いつでも母校に帰ってきてください。母校は皆さんのもう一つの実家です。これからの100年、社会に新たな価値を生み出すため、ともに歩んでいきましょう。 卒業式の壇上を華やかに彩ってくれたお花は、フラワーアレンジ部が心を込めて作成してくれました。現在は事務所前に飾っています。
