忘れ物・落とし物(20230222)
年度末が近づき、生徒諸君の忘れ物・落とし物の整理をしましたら、メガネがいくつも保管されていて、驚いています。 私は、メガネをしているのに「メガネが無い!」と騒いで探し回った経験があるくらい、メガネの紛失は一大事という感覚がありますが。
明日から試験(20230220)
修学旅行が迫っている3年生は、早くも明日から学年末試験です。 教室には、明日からの試験に備えて時程表が貼り出されていました。 まずは落ち着いて、しっかり試験勉強をしてほしいと思っています。
YOMOCA2月号&猫の日
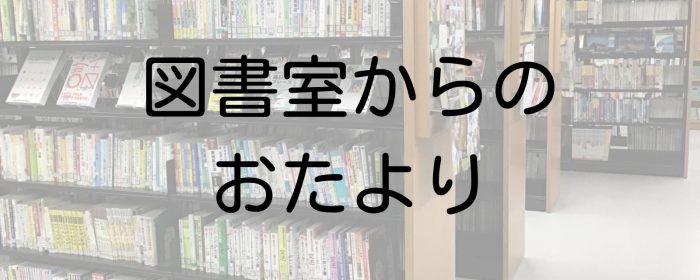
先週、YOMOCA2月号を配布しました。 ブログでは、表面のみのご紹介です。 裏面は新着図書の紹介、捜索中の図書、まちがいさがしです。 YOMOCAでも予告していますが、猫の日とYOMOCA222号にちなんで! 2月22日限定で、本を借りた人へ猫のしおりを1人1枚プレゼントします。 (図書委員生徒から「2022年じゃなくて惜しかったですね」とのコメントをもらいました。残念ですが、2023年「にゃーにゃーみゃー」ということにしておきましょう……) しおりは全部で6種です。お好きな猫を連れて帰ってください。 数量限定なので、品切れの際はごめんなさい。 猫に関する本も展示予定です。2月22日はぜひ図書室へ! 図書室 伊達木
6年担任の落ち着かない日々
今日あたりが私立大学の合格発表のピークでしょうか。職員室の6年担任の席から小さな声が上がる度に、気になってそちらを見てしまいます。担任団が笑顔ならもちろん嬉しいですし、難しい顔をしていればそういうことなのだと理解しますが、早い時間に残念メールを送ってくれる生徒はまだ少し安心。担任は励ましのメールを返すのと同時に、連絡のない生徒を心配しながら待ち続ける。そんなここ数日です。 私立大学の入試はそろそろ終盤で、来週の今日はいよいよ国公立大学の前期入試日です。1ヶ月近くに及ぶ入試期間で精神的に辛い時期でしょうが、6年生の健闘を祈るばかりです。 4,5年生の授業を覗くついでに、6年生の5階フロアへ上がりました。2、3名が教室で勉強していましたが、廊下はガランとしています。しかし、大きな経験をして、喜びも悲しみも乗り越えて成長した生徒たちが、ちょうど1ヶ月後に全員このフロアへ戻ってくるはずです。
内側から解体(20230217)
解体工事中の旧東棟は、通常とは少し違った方法で解体していると担当の方から聞いたので、しばらく眺めていました。 建物がコの字型に地下体育館(の屋根=中庭)を囲むように建っていたのを、体育館からまず解体し、その後周囲の建物を内側から壊していって体育館に残骸を溜めていき、地表面と同等に平らにして作業をしやすくしてからさらに周囲の解体を進めるというのです。 全部壊した後で全て掘り出して綺麗にして、新校舎の建築を始める、と。それが一番コストのかからない方法なのだそうです。 なるほど、すっかり地下体育館は埋まって平らになっており、残った建物を内側から崩しているので、外壁が最後に残っている様子が見えます。 こういうのを考えて実行するのは楽しそうです。
続・生け花(20230216)
職員フロアの片隅に、授業で使った花材の余りを教員がアレンジして活けていました。 授業が終わって1週間経ちますが、まだまだ私たちの目を楽しませてくれています。
あと2週間(20230215)
6時間目の総合学習の時間に校内を歩いていましたら、体育館からニュージーランド国歌が聞こえてきました。 現地校での交流会に向けて、3年生が全員集まって「出し物」の練習をしていたのでした。 私も4回引率していますから、(歌詞を見ればですが)歌えます。
図書委員広報班より(おすすめの本紹介)
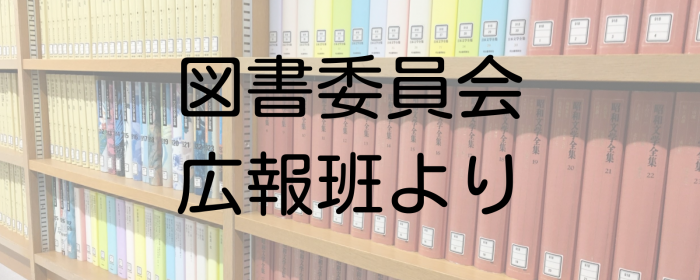
図書委員広報班よりおすすめの本の紹介です。 『ハリー・ポッターと賢者の石 1-1』 『ハリー・ポッターと賢者の石 1-2』 J.K.ローリング:作,松岡佑子:訳/静山社(静山社文庫) ※単行本もあります ※英語版もあります 幼くして両親を亡くし、孤独な日々を送っていたハリー・ポッター。彼は11歳の誕生日に驚くべき手紙を受け取った。 この手紙がありふれた日常を、宿命に操られる波乱の人生へと変えていきました。 ホグワーツ魔法魔術学校で新たな生活を始めたハリーを次々と闇の恐怖が襲う。勇気と信頼と友情の物語がここから始まる。 この作品は私たちの日常では考えられない、不思議なことが沢山起こります。その一つ一つがとても繊細に描かれているため、自分自身もその場にいるような体験が出来る作品になっています。ぜひ読んでみてください。 図書委員広報班3年
新学年の下校延長はじまる
今年から4,5年生に拡大して下校時刻の延長が始まりました。初日の昨日は2学年合わせて50名以上が残り、窓の外がすっかり暗くなった教室で学習を続けていました。途中で様子を見に行ったのですが、扉から覗いてもこちらを見る生徒は数えるほど。みんな集中しています。今後、時期によって参加者の増減はあると思います。しかし、終礼が終わった時に、その日は何をどこで勉強するかが決まっている生徒は取りかかりが早く時間が多く取れますから、この制度をうまく使って学習習慣を確立してほしいと思います。 そして今日はバレンタインデー。生徒にとっては大きなイベントだと思いますが、昨今の状況ですから学校への持参、交換は遠慮してもらっています。最近はこのイベントの捉え方もさまざまですが、普段から支えてくれいる人のことを思って準備するという気持ちは変わらないようです。 少し前の卒業生になりますが、大手スーパーのバレンタインギフトを扱う店舗に毎年大きな絵を提供しているという話しを聞きました。イラストレーターとして活躍している女性で、在学中からとても個性的でした。今日が最終日だと思いますが、もし行くことがあったら以下にリンクを貼りますので、注目してもらえたらと思います。 https://www.itoyokado.co.jp/special/valentine/?fbclid=IwAR1QCQIOgM-H40gra_dsMg0osE6fCMeMtDQqZl7n6yV5n_p14toRrshS_Pc
