事後研修
先週土曜日にヨーロッパ研修旅行の事後研修が行われました。平和・芸術をテーマとしたプログラムだったのですが、同時期に同様のテーマで研修を行っていた鎌倉学園の男子生徒さんを招いてのワークショップです。 両校生徒とも比較的早い段階から打ち解けて積極的に意見交換をしていました。共通の話題があるので話しやすかったのだと思います。同行したメンバーとだけ話をしていると思い出話しになりがちですが、他者の視点が入ることで、自分たちの経験を違った角度で見ることができます。 話し合いの前には、両校の代表者によるプレゼンテーションがありました。「シェーンブルン宮殿の天井画があまりにも印象的だったので友達に写真を見せたら、サイゼリヤの天井に似ていると言われた。」とサービス精神旺盛な本校生徒はオチまで作って準備していたようです。
PTA運営委員会(20240907)
役員の皆様が、暑い中お集まりくださいました。 今回は、理事長から長めの話がありました。 私は、近況報告のご挨拶を少しだけ。 (笑いをとる理事長の図。もちろん、内容は真面目な話。)
戻ってきた(20140906)
ここのところ少し過ごしやすくなってきたな、と思っていたら、まだまだ夏は過ぎ去っていませんでした。 土曜日はさらに暑くなるような話を聞いております。やれやれ。 夕刻、そろそろ帰ろうとしていたタイミングで、卒業生が来校しました。 1時間立ち話をしていきました。95%くらい聞き役でした。 まあ、話したいこともありますよね。まだ話し足りないようだったけれど、また来てください。 (午後の屋上)
2学期の学校説明会(20240905)
夏休み中はショートバージョンを13回実施しました。 今日からまた、フルバージョンです。 校舎工事中のため狭い会場しかご用意できなくて毎度心苦しく思っているのですが、今日の来校者アンケートに「距離が近く感じられて良かったです」と書いてくださった方がいて、ほっこりしました。ありがとうございます。
YOMOCA9月号
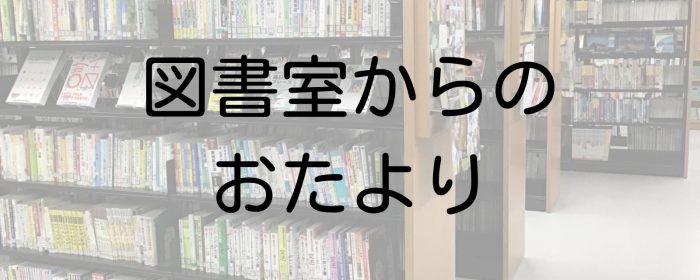
2学期が始まりました。 2学期最初の図書委員会でYOMOCA9月号をお配りしました。 文化祭明けから、いよいよ図書室の移転準備が始まります。 利用に影響がありますので、よく確認してください。 なるべく生徒のみなさんへの学習支援が止まらないような形で進めたいと思っています。 しばらくの間ご不便おかけしますが、よろしくお願いします。 図書室 岩崎
今週の総合学習
今日の総合学習は4年生が文化祭準備、5年生は個人探求の中間発表、6年生は共通テスト出願のガイダンスでした。 5年生は班に分かれて自分の研究経過を報告しあい、その後代表が全体に向けて発表するというもの。盛り上がっている教室の後半部分を覗かせてもらいました。 例年にも増してテーマが面白いです。そして私が聞いた発表の多くが、あるテーマについての日本と外国の違いにターゲットを当てていました。マンガの描き方や外国語学習の方法、擬音擬態語の表現方法や刀の制作方法の違いに注目している生徒もいました。 自分たちには当たりまえのことが、外国人にはどう見えていて、その背景にある考えは何なのか。私も中高生時代に興味があったので、一時期そのような本ばかり読んでいた記憶があります。これからそれぞれがどんな研究へと発展するでしょう。とても楽しみです。 刀をテーマに選んだ生徒の発表。すでに4か所の博物館を訪れたそうです。
実証実験(20240904)
文化祭まで2週間と少し。 実行委員会が校内の一角で何やら実験をしていました。 文化祭で使える設備かどうか、試しにやってみないとわからない、ということでしょう。 何でも、やってみることは大事です。 サッと出してサッと片付けられていましたが、いいデータは取れたでしょうか。
言いたいことを一つだけ、でもなかった(20240902)
今日から2学期がスタートしました。 始業式は、理事長から・表彰二つ・留学生の紹介とメニューが多かったので、私からは一番言いたいことを一つだけお話ししました。 と言いながら、つい「台風10号が紀伊半島沖で熱帯低気圧になった」というニュースに「温帯低気圧じゃないのか!」と驚愕してモヤモヤが消えない、と話の枕を置いてしまいました。 本当に驚いたので・・・。 それでも、枕も含めて全部で3分くらいしか話していないと思いますが。 夏休み、うまく過ごせなかった、成果を出せなかったという人も、大丈夫、「次」を考えて2学期をその機会にしよう、というのが一番言いたかったことです。 皆さん、大丈夫ですよね。 (今日も特別講座が実施され、多数のゲストがおいでくださいました)
始業式・表彰・登壇お知らせ

本日から2学期です。体育館で中・高それぞれ始業式がありました。 まずその前に、久しぶりのホームルーム。その後は、防災訓練でした。夏休み中には「南海トラフ臨時情報(巨大地震注意)」も出され、防災への意識も高まっていると思います。今回は「地震、その後に調理室で火災が発生した」という設定です。 始業式では、2学期からの受け入れ留学生の紹介もありました。今回はフランス、アメリカ、アイスランド、ドイツからの留学生です。およそ20年にわたり受け入れプログラムを行っていますが、アイスランドからは初めてです。それぞれ練習してきた日本語でのあいさつに加え、英語でも挨拶してくれました。高校1年生のクラスに所属しますので、皆さん、声をかけてくださいね。卒業後にはお互いの国を行き来するほどの仲になる先輩たちもたくさんいます。 夏休み中には大会や合宿などで活動したクラブがたくさん。コメントももらいました。 *中等部表彰【ダンス部】第 12 回全日本小中学生ダンスコンクール東日本大会 金賞 【吹奏楽部】第 64 回東京都中学生吹奏楽コンクール B 組 銀賞 *高等部表彰【ECC 部】PDA 全国高校生即興型ディベート大会 2024 チーム 4 位PDA 全国高校生即興型ディベート大会 2024 ベストディベーター賞PDA 全国高校生即興型ディベート大会 2024 ベスト POI 賞 【ダンス部】第 12 回全国高校ダンス部選手権全国大会 オーディエンス賞 【吹奏楽部】第 64 回東京都高校生吹奏楽コンクール C 組 銀賞【書道部】東京都高等学校文化連盟書道展 奨励賞 《登壇のお知らせ》ダイバーシティーリーダシップの話を女性リーダーの皆さんとします。 “INSPIRE SESSION” - Beyond Diversity - 多様性を活かし、勝つ組織づくりとは? ◆開催日時2024年9月26日(木)19:00~20:30 ※18:30より開場予定 ◆開催会場代官山 蔦屋書店3号館2階 シェアラウンジ内イベントスペース(オンライン参加もあり)有料です。 詳細はこちら
