特別講座〈新井和弘さん×池上彰さん〉(20230612)
池上彰さんは、8年ほど前にも本校に来てくださり、そのときは私も授業をご一緒しました。 今日は私は裏方で、教室の隅で拝聴しておりました。 コメントのキレはお変わりなく、生徒だけでなく私も勉強になりました。 新井さんには打ち合わせ段階からお世話になり、授業構成にも本校の要望を取り入れてくださいました。 感謝申し上げます。 (池上さんから笑いをとる、さすがの品女生)
2年生保護者会(20230610)
学年の保護者の皆様全員にお集まりいただく場所がなかったので、私からのお話は各教室に映像でライブ放送しました。 直接お目にかかれなかったのは残念ですが、クラス報告会やその後の懇親会では、保護者の皆様どうし親睦を深めていただけたようで、よかったと思っています。
図書委員会広報班より(おすすめの本紹介)
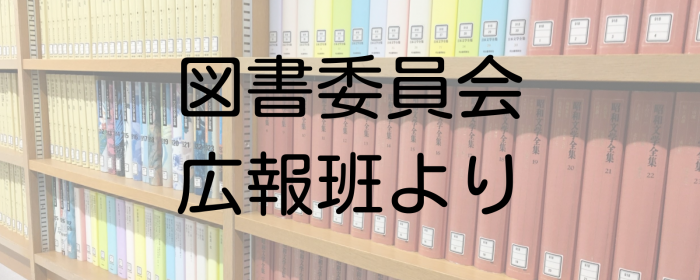
図書委員広報班より、おすすめの本の紹介です。 『怠けてるのではなく、充電中です。 昨日も今日も無気力なあなたのための心の充電法』 ダンシングスネイル:著 生田美保:訳(CCCメディアハウス) 『死にたいけどトッポギは食べたい』ほか、韓国で多くのベストセラーになった本のイラストを描いた‘ダンシングスネイル’によるエッセイ。 何をしても面白くないし、すべてが面倒くさい。心は憂鬱だけど、わざと明るいふりをして笑う。何もしてないのに心が疲れてる。将来が不安で眠れない。そんな誰にでも訪れる人生のスランプを克服する心の充電方法。 表紙のイラストが可愛くて手に取ったのがきっかけのこの本ですが、読めば自分の心に寄り添い、物事の新たな見方や考え方を教えくれるあたたかい本です。 この本を読めば、今以上に自分のことをもっと好きになれると思います。 ぜひ読んでみてください! 図書委員広報班4年
逆境を楽しむ(パラスポーツ、ユニバーサルマナー、ドローン、体育祭)
生徒と同年代、車いすテニスの小田凱人選手が話題になっています。子どものころはサッカー少年で、骨肉腫の闘病生活の後、車いすテニスを始め、現在、世界的に活躍しています。 東京オリンピックの招致に貢献したパラリンピアンの谷真海さんも(サンデースポーツ担当、朝礼でもお話していただきました)チアリーディングの選手から骨肉腫を発症したあと、パラスポーツに転向し、『ラッキーガール』という著書を出しています。 パラアスリートの活躍を見ていると自分の置かれた状況を受け入れてどう次へ進むかということを考えさせられます。 昨日は、シンクロメダリストで心理学者のウルヴェ田中京さんのセミナーに出ていたのですが、スポーツ選手のセカンドキャリアの話になり、目指すもののある人は、次の目標に向かってそれまでの力を転換できるというような話題になりました。(スポーツ×ヒューマンの村田諒太さんとのメンタルトレーニングのセッションは感動しました。村田さんの最近の著書も) 実は、ここ数ヶ月、いつも頭が酔っているような症状が出て、いろいろな診療科に行っても原因不明で困っているのですが、スポーツ好きの私はこうしたアスリートの前向きさにインスパイアされ、この状況にも先行き人にシェアできる意味が出てくるのはないかと思っています。 さて、本校では、東京オリンピックまでに全員が経験することを目標に、「ユニバーサルマナー」の研修を受けています。ミライロの垣内さんとの出会いがきっかけでした。 以下は、昨年の中一の研修の様子を主任の直井が報告してくれたものです。 ユニバーサルマナーとは『自分とは違う誰かを思いやり、 適切な理解のもと行動すること』。 知らない、わからない、という「ない」からくる不安をなくし、「 なにかお手伝いできることはありますか?」 とコミュニケーションをとろうとする気持ちが大事であることを、 ワークや身近でわかりやすいお話を通して、 教えていただきました。 事前学習では、「 街で見かけた人が不便や不自由を感じているときに、 何か行動したことはありますか」という質問に、「 行動しようと思ったが声をかけられずに後悔した」 と書いた生徒がたくさんいました。 今回の経験が「なにかお手伝いできることはありますか?」 という言葉をかけられる勇気につながることを期待しています。 もう一つ、ご紹介したいのは、ドローンスクールを開講する卒業生のことです。特別講座もしてくれたのですが、そのときの「ドローンは身体の拡張性の可能性を広げる」という話が響きました。男性より筋力の弱い女性であっても、障害があってもドローンのテクノロジーを活用することによって活躍の場が広がるということです。特別講座のとき担当した住谷へ以下のような報告があったそうです。ドローンの事業と同時に国際貢献事業も行っているというマルチな卒業生です。津田塾から東大の大学院へ進学し視野を広げたことも奏功したのかもしれません。 最近は、専門性を磨くため、大学院や留学という選択肢をとる子も増えてきました。28プロジェクトを始めてからの卒業生の仕事の多様性をうれしく頼もしく見ています。(以下引用) 国家資格が取得できるドローンスクールとして、 国交省から登録講習機関の認可をいただいたので、 うちのスクールで受講すれば実技試験が免除になる仕組みです。 また、開校地である大島町とは「 無人航空機に関する包括的連携協定」を提携し、 町ぐるみで協力していただく体制になっております。また色々仕掛ける予定でいますので、 また品女に話を持っていく際にはどうぞよろしくお願いいたします 。おしんドローンスクールHP(まだ公開したてで、 これからいろいろ情報をまた変えていきます)(と、開校前で忙しいのですが、 今月8年ぶりにクーデター中のミャンマーに出張で行く予定です。パキスタン事業も遠隔で色々動いてます。また近況報告します) 体育祭の報告はしましたが、写真をもらったので、アップします。 在校生達もコロナ禍の状況を受け入れ、マジックハンドのパン食い競争など様々な工夫をこらして、一年一年この行事を継続してきました。 卒業後の人生にもいろいろなことがあると思います。輝る日もあれば曇る日もあるでしょう。でも、どんなときも品女での学びとつながった縁が、巣立っていった彼女たちを支えるように、学校も常に前に進んでいたいと思っています。どんなときも戻ってこられるもう一つの実家として。 開会式 徒競走 玉入れ パン食い障害物競走 長縄 棒引き ビーチフラッグ クラブ対抗リレー 私も放送席から実況中継 3年演舞 着付けコンテスト 綱引き 宅配便リレー メディシングボール 借り物競走 ハッとしてピョン 学年対抗リレー 閉会式 6年生優勝 体育祭実行委員
卒業生に感謝の1週間
今週はほんとうに多くの卒業生が本校の活動を手伝ってくれました。いくつかご紹介します。 (月曜日)74期の卒業生が高等部生向けの特別講座を開いてくれました。インターン先の社長さんを講師にお招きして、自己診断とライフデザインに関するディスカッションが行われていきます。時々自分を再発見する鋭い質問が投げかけられました。2回目が来週行われます。 (火曜日)都立大大学院に通う70期の卒業生が、自分が行っている活動を紹介してくれました。インダストリアルアートの研究しているのですが、海洋汚染問題の解決策の一つとして自分の活動が生かせるのではないかという話でした。リンクを貼りますので興味のある方はそちらを見てみてください。また渋谷スクランブルスクエア東棟ビジョンでも、研究作品の展示が行われているようなので、近くに行ったら注目してあげてください。 https://jinkai.jimdofree.com/?fbclid=PAAaYAQybpg5yZf7JY3tiWenWUZ98YKxvTyncUUV_8iCO2c2KBevCF-RDc-pw 工事中の旧東棟敷地を見てちょっと寂しそうでした。 (水曜日)卒業生ではないですが、日本ユースリーダー協会のツアーに参加しているタイの高校・大学生7名が交流のために来校されました。本校生徒と一緒に昼食をとったり、化学の授業を受けたり、最後には茶道部の活動にも参加しました。 [gallery size="medium" columns="2" ids="32163,32162,32161"] またこの日は、留学出発時に生徒にアドバイスをくれた航空会社職員の卒業生も来校していました。彼女は7年も前に起業体験で作った商品を今でも大切に使っていると言って見せてくれました。 (木曜日)この日は卒業生の特別講座がなんと2つも。昨年卒業した75期と73期の卒業生です。どちらも自分の未来について考える講座です。2人とも後輩が将来を考える手助けをしたいという気持ちが強いのだと思います。ありがたいことです。また、デザイン系の学校に通っている卒業生も近況報告に来てくれていました。この系統は学校に情報が多くはないので、もしこれを読んでいる生徒でアドバイスが欲しいという生徒は、私が繋ぎますので言ってきてください。 (土曜日)今日は73期の卒業生が、自習室のチューターとして来てくれます。忙しい大学生活の中、2人とも後輩のために4週間連続(試験中を除く)で来てくれます。せっかくですから、中等部の生徒も高等部の生徒もどんどん質問しにいってほしいと思います。
中1デザイン思考授業Part.2〈続〉(20230609)
今年はせっかく導入授業の2回目をやることになったので、「インサイト」というちょっと難しい概念を扱ってみることにしました。 呑み込みの早い人たちで、核心を衝いた感想が多く見られ、驚いています。 (一例)
YOMOCA6月号
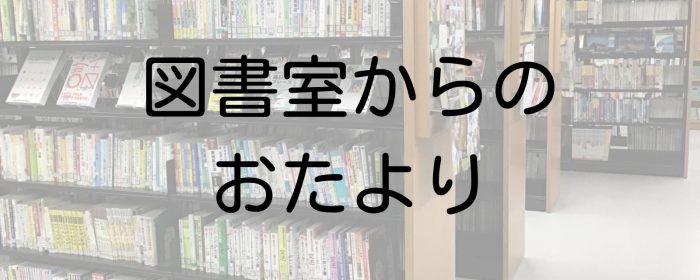
テスト明けの委員会でYOMOCA6月号を配付しました。 今回は 督促状が届いたら…… 図書委員会広報班のおすすめ本紹介 図書委員会装飾班の活動紹介 図書室ってこんなところ! 裏面は紙書籍・電子書籍の新着紹介とまちがいさがしでした! (ブログには表面のみ掲載しています) 意外と図書室って便利なんだ!と知ってもらえたら嬉しいです。 図書室 岩崎
中1デザイン思考Part.2(20230608)
今年は、宿泊行事の際だけでなく、もう1時間プラスしてデザイン思考の導入授業を実施し、こちらも私が担当しました。 学校説明会の開催もありましたが、授業優先ということで、私のパートは火曜日の説明会の様子を撮影したビデオでご容赦いただきました。 4時間目の授業中に、見学の方が回って来られたとき、私の授業では、ちょうど某ラーメン屋さんのカウンターの写真がプロジェクタで映写されていました。 安心してください。歴とした教材(自作)の一部です。 (証拠:生徒のワークシート)
中等部朝礼(20230607)
帰国する留学生から挨拶のスピーチがあり、そのあと私からお話。 KURKKU FIELDSの新しい施設を見て考えた「コンセプト」と「らしさ」について。 〈言及した本〉 『風の谷のナウシカ』宮崎駿 『中動態の世界』國分功一郎 『希望の歴史』ルトガー・ブレグマン 『東京の生活史』岸政彦 編 『言葉を失ったあとで』上間陽子・信田さよ子 『体はゆく』伊藤亜紗 ほか
